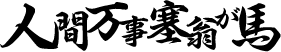十三の杖
(メモ)
1→2
上段返し打ちは、はじめは1・2の2拍で体の一致を図る。
急がず等倍速でやる。なれてきたら1と2の間をなくす。
振り上げの頂点で一旦止まるのではなく、頂点に到達する時にはすでに振り下ろしが始まっている。さらに上げるには、右半身を前に送る動きと、左半身を引く動きを同時にやる。そうして最終的には1拍で動けるようにする。
速い動きとは、杖を早く振ることではない。
これは剣の正面打ち連続の動きと同じ。
3の受けは三角帯で受ける
(31の杖は水平にすくい上げて上から叩き落とす)
3→4は引かずにそのまま押し込んで崩す
9の引き杖は上段を空けて誘いに使う
(よって10は上段払いになる)
12の持ち替えの時は、引かずに右に体を捌く。
(プレミアムタイム)
力を相手に作用させるには3つの方法がある
①体重移動
②波
③直接意識を持っていく(合わせ?)
これって技術レベルもそういう順番ではないかと感じる。
体重移動は一番わかりやすいし、体の操作もしやすい。その分大きく動くので隠すことが難しいのではないか。
波は体の中の重心の移動(おそらく支点揺動)なので、重心移動を体の中で行うため少し難易度が上がるが、物理的な位置関係は変えなくてすむし、接触面さえ変えなければ読まれづらい。また慣れてくれば体の中の波を最小限に隠すこともできそう。
それでも「波」はタイムラグが出る分遅い(と先生はおっしゃる)ので、直接作用する技術が出てくる。まだ体感的な理解が得られないが、
波が最小限の動きになった動き
波の出力が完成された状態で接触する
ということも考えられなくはない。ただ普段の合わせの稽古をやっていると
崩す所を意識するだけ
という感覚もある。
いずれも接触面に変化を与えず、相手に察知されないことが肝要。
宮平保の手は引きながら突くを先生が体現。すごいとしか言いようがない。